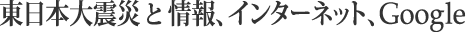パーソンファインダーや自動車・通行実績情報マップなど、東日本大震災において Google が行ったさまざまなクライシスレスポンス(災害対応)は、インターネット上のメディアだけでなく、新聞やテレビといったマスメディアでも大きく報道された。
エンジニアがスピーディにサービスを開発できたからこそ、クライシスレスポンスは可能になったわけだが、これらのサービスは大勢の人に使ってもらって初めて意味を持つ。新聞やテレビを通じて Google のクライシスレスポンスを知った人は少なくなかったが、その影には、できる限り多くの人にサービスや情報を届けようとした、マーケティングや広報の担当者の奮闘があった。
2011年3月11日(金)の 14:46 までは、当然のことながら誰もがいつも通りに仕事をこなしていた。例えば、広報部の富永紗くらは新サービスについての社内向けレポートを自分のデスクで作成していたし、馬場康次、須賀健人らマーケティングチームは、3 ヶ月を費やした大型キャンペーンの最終段階にあり、CM の制作作業やクライアントとの打ち合わせに忙殺されていた。
突然の巨大な揺れに驚いた Google 社員達だったが、これまでの記事で紹介してきたように、16:32 にはクライシスレスポンス特設ページを立ち上げている。この後、社内のコタツエリアの回りに集まった社員同士、あるいは社内メーリングリストにおいて活発な情報交換が始まり、クライシスレスポンスの活動は本格的になっていく。
混乱した状況の中、広報部の宮家かおりはクライシスレスポンスの始まりを告げる記事を公式ブログにアップ。その後、富永らは公式ブログや Twitter の公式アカウントを通じて、矢継ぎ早に生み出されるサービスの告知に努めた。またマスメディアに対しても、クライシスレスポンスが始まったことをメールや電話、FAX 経由で伝えていた。
社内に残っていたマーケティングチームは、進行中のキャンペーンに関する作業はそのまま進めつつ、情報収集などクライシスレスポンスの手伝いも並行して行い始めた。CM の調整作業を進めていた馬場は、震災によってキャンペーンがなくなるのではないかと感じていた。
 Crisis
Response
Crisis
Response