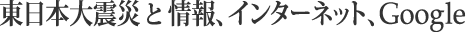東日本大震災が起こり、被災地の住民は日常生活でもさまざまな苦労を強いられた。避難所ではトイレや入浴設備が行き届いているとはいえなかったし、水や食料も潤沢に供給されていたわけではない。車が唯一の移動手段である地域では、ガソリン不足が深刻な問題になった。ガソリンの販売があるという噂が流れると、その店の前には開店時刻のずっと前から長い行列ができたが、並んだからといってガソリンを買えるとは限らなかった。
被災地の人々は、食料や給水、ガソリンなどについての信頼できる情報を喉から手が出るほど欲していた。Twitter や Facebook では、断片的に情報が上がっていたが、分散している情報を探すのは大変な労力がかかってしまう。電力供給が不安定でネット回線にもダメージを受けている地域では、パソコンで丁寧に情報を探す余裕もない。
こうした不便を少しでも減らそうと、Google は「被災地生活救援サイト」を立ち上げた。実は、このサービスは数多くのボランティアと Google の共同作業によって生まれたものである。
震災が起こった時、モバイル検索エンジニアの今泉竜一は、六本木の Google 東京オフィスで同僚と打ち合わせをしていた。揺れに驚いた今泉だったが、進行中の仕事を仕上げると、パーソンファインダーの翻訳作業などを手伝い始めた。
週が明けて14日(月)、今泉らモバイル検索チームは、検索結果の検証を行っていた。震災に関係しそうなキーワードをピックアップし、同僚と共に手当たり次第に検索をかけていった。マスメディアでは被災地で水や食料が不足しているという情報が盛んに流れていたが、モバイル検索の結果には被災地にとって有意義なサイトがあまり上位に来ていなかった。
Google 検索では、パソコンからと非スマートフォンの携帯電話、スマートフォンで検索結果が異なる。携帯電話から検索を行う場合、携帯電話向けに最適化されているページの順位は高くなる。パソコン用に作られたページを見られる端末もあるが、使いやすいとはいえない。
そこで、Google で携帯電話向けの有意義なサイトをピックアップして、検索結果ページからそれらのサイトに誘導することになった。
今泉らは、物資やインフラなどの生活面にフォーカスして情報収集を行おうとしたが、被災地の人々が本当に必要としているのは、地域に密着したピンポイントの情報である。Twitter などで断片的な情報は上がってきても、それらの情報を網羅するのは困難だ。
何かよいサイトはないか。そんな時に見つけたのが、及川雄一さん(ハンドル名:UPYON)が作成していた生活情報のまとめサイトだった。
 Crisis
Response
Crisis
Response