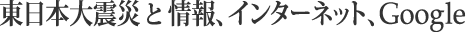楽しい時でも、悲しい時でも、不安な時でも、おなかが減るのが人間だ。そして、空腹が続くと人は惨めな気分になる。
逆に、おいしい食事を取って、暖かくして、誰かといっしょにいられるのなら、困難に立ち向かう気力も湧いてくる。
東日本大震災では、食事のありがたさを改めてかみしめた人も多かったのではないだろうか。
被災地の避難所では、十分な食料が行き届かず、辛い思いをした人がたくさんいた。首都圏は損害が少なかったにも関わらず、震災の翌々日から、コンビニやスーパーの食料品が消えてしまった。不安に駆られ、目に付いた商品を片っ端から買い占めていった人がいたことは記憶に新しい。現代の日本において、食べ物の不足に脅える状況は久しくなかったことである。
震災直後から六本木の Google 東京オフィスではクライシスレスポンスが始まっており、パーソンファインダーの立ち上げ、特設サイトの制作、種々のサービス開発、情報収集と、Google 社員達は寝る間も惜しんで作業に没頭していた。そんな彼らの励みになったものの 1 つが食事だった。クライシスレスポンスについて Google 社員に取材していると、震災当日の夜食に出たパスタに救われたとみなが口を揃えて証言する。
Google という会社は、ふだんから食事を重視することで知られている。東京オフィスにも広いカフェテリアがあり、和洋中の料理が何十種類も並ぶ。デザートや飲み物も豊富に揃っており、社員はこれらを無料で自由に飲み食いできる。Google 創業者のラリー ペイジ(Larry Page)は「仕事場と食べ物は 150 フィート以上離れていてはならない」という信念の持ち主だ。
筆者らも取材にかこつけて何度かカフェテリアでご馳走になったが、無料とは思えない料理のバリエーション、そしておいしさに驚かされた。ちなみに、筆者(山路)は、マンゴープリンがお気に入りだ。
東京オフィス内には、カフェテリア以外に 7 箇所のマイクロキッチンがあり、飲み物やスナック類、果物、サンドイッチなどの軽食が用意されている。
これほどカフェテリアやマイクロキッチンが充実しているのは、社員達が食いしん坊なせいもあるが、コミュニケーションスペースとしての役割を担っているからである。社員同士がコミュニケーションを取るきっかけが社内の随所に用意されているのが、Google の特徴だ。
東京オフィスのカフェテリアを管理するのは、フードマネージャーの荒井茂太である。荒井は数十名ものフードスタッフを指揮し、メニュー作り、食材の仕入れ、衛生管理などの業務を日々こなしている。
「『食』はとても大切です。ただ腹を満たすというだけでなく、おいしい食事があるから、カフェテリアやマイクロキッチンに集まろうということになるでしょう。社員のみなさんが部署を超えて会話をし、そこからイノベーションが生まれて、新しいプロダクトにつながっていく。私たちもそのプロセスに関与したいと思っており、おいしく楽しい食事を提供するよう意識していますね。私自身が厨房に立つこともありますが、できるだけカフェテリアの外に出て、Google 社員の要望を取り入れようと心がけています」(荒井)
 Crisis
Response
Crisis
Response