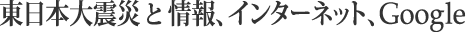この連載では、ウェブを始めとする IT によって、どのような災害対応が可能になったか(あるいはなりえるのか)をレポートしてきた。今回は、デジタルで記録を残すことの意義について改めて考えてみたい。
何百年も前の文書に記された地震や津波の記録によって、災害規模や避難方法に関する貴重な知見が得られるのはご存じの通りだが、デジタル技術による記録は媒体をたんにハードディスクやメモリに変えただけではない。
IT を用いてデジタルで記録することの目的は、おおまかに 2 つに分けられる。
1つは、紙やフィルムなどに記録するのと同じく、人間が見聞きするため。そしてもう1つは、コンピュータで利用するためである。
まず、人間が見るための記憶ということについては、写真や動画などのアーカイブが挙げられる。
Google では、第 21 回でも取り上げた「東日本ビジネス支援サイト」などの取り組みを 4 月下旬頃から開始していたが、そうしたビジネス面以外にもデジタルアーカイブで復興支援を行おうというアイデアが Google 社内から出てきた。それは、被災地の「記憶」を取り戻すということである。
「震災前におじいさんといつも行っていた公園とか、友達といったお祭りとか、そういった失われた記憶をもう一度思い出すことができれば、復興の力になるのではないかと考えました」(プロダクトマーケティングマネージャー 須賀健人)
その頃、津波で汚れてしまった写真をきれいにするボランティア活動なども始まっていたが、インターネットに強みを持つ Google の力をうまく活かせる方法はないか。
そこで利用されたのが、写真共有サービスの Picasa ウェブアルバムである。一人一人が持っていたリアルなアルバムを取り戻すことは、Google にはできない。けれど写真を通じ、同じ経験をした者同士で、記憶を共有する手伝いならできるはずだ。
5月末、Google のマーケティングチームは、「未来へのキオク」と名付けたサイトをオープンした。このサイトでは写真なら Picasa ウェブアルバムに、動画なら YouTube に、誰でも投稿することができる。また、特定の写真や動画を探している人が、関連する場所やテーマを指定して募集することも可能だ。2011 年 5 月から 2012 年 2 月までの間に、552件の募集テーマが立てられ、これらのリクエストに対して 5 万点以上の写真や動画が全国から寄せられた。中には1950年代に撮影された写真もあったという。
「祭りや花火大会などハレの写真が多かったのですが、地元の中学校や商店街の写真が欲しいというリクエストもありました。普通の学校生活、普通の公園など、毎日の暮らしが映っている写真は、とても印象的でしたね」(須賀)
同時期、Yahoo! JAPAN でも「Yahoo! 東日本大震災 写真保存プロジェクト」を始めていた。10 月になると、GoogleとYahoo! JAPANは協力関係を進め、どちらかのプロジェクトに投稿された写真は、他方からも見られるようにした。
 Crisis
Response
Crisis
Response