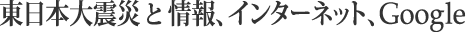河合は飛行機の手配と同時に、Google 東京オフィスの藤井宏一郎に連絡を取った。藤井は、政府との交渉ごとや政策回りの案件といったガバメントリレーション(GR)を担当している。彼は、地震直後に採用面接をしていたが、面接相手を帰宅させた後、会社から徒歩圏にある家に一時帰宅した。河合からチャットで連絡があったのはその時だ。
「河合は、飛行機を飛ばして写真を撮りたいって言うんですよ。『この大災害の中、何を言い出すのか。テレビを見ても状況がわかっていないのか?』と思って、最初は『無理だ』と返しました。ところが、河合が引き下がらないので耳を傾けてみると、被災地の状況をいち早く捉えて世界に知らせることこそが Google のミッションだと言うんです」
これをきっかけに、藤井も 24 時間態勢でクライシスレスポンスに当たることになる。国土交通省の国土地理院にアプローチしたところ、実は国土地理院もすでに航空写真を撮影する準備を進めており、数日以内にウェブページ上での公開も予定していた。しかし、Google マップや Google Earth で利用できる、高精細のデータを提供してもらうためにはさらに時間がかかるということがわかってきた。
藤井は、なんとか写真を入手できないかと国土地理院と何度かメールや電話でのやり取りを繰り返したが、国土地理院の航空写真を入手して活用するためには、どうしても「測量成果の複製・使用」と言うウェブページから申請書をダウンロードし、返信用切手を貼って郵送し、最大で 2 週間待たなければならないことがわかった(なお、国土地理院は Google のリクエストに応えるつもりだったが、途中で交渉が途絶えたという認識でいる。コラム参照)。
これでは、被災地の現状が心配な人たちや救援に向かう人たちのため、早く簡単に利用できる写真を提供したいという河合の要請に応えられない。
「とにかく早く提供することが大事」――この信念の元、国土地理院との交渉と並行して、パートナーシップ担当の村井説人も、航空写真を提供する企業にコンタクトをとり、手続きなどを調べてもらっていた。しかし、これらの会社が所有する飛行機は、政府の目的のために予約済みであった。
こうした経験を経た村井は「有事の際にどういうプロセスが必要かを検討し、Google も事前に参加しておくべきだったというのが、今回の気づきの一つ」だと語る。
藤井は、その後も国土地理院と連絡を取り続けた。しかし、13 日の朝になると、これ以上交渉を続けるよりも、Google が独自に手配した飛行機で航空写真を用意した方が近道だと判断し、それを河合らに伝えた。
自分たちで飛行機を手配する方針を固めたものの、それを実現するためには長い長い折衝が待っていた。結局、最初の飛行機が仙台上空を飛んだのは、2 週間後の 3 月 27 日だった。それまでの間、藤井はいつかかってくるかわからない河合や政府機関からの連絡を逃すのが心配で、地下鉄に乗ることができず、どこに行くにもタクシーで地上を移動していたという。
 Crisis
Response
Crisis
Response