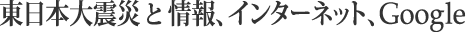震災直後の Google が、プロジェクトを進めるかどうかの判断基準にした材料は、上記の「クリティカルで効果があるか」と「利用者が活用できる情報か」かのほかに、もう 1 つある。それは「他社がやっていないか」だ。
クライシスレスポンス特設ページでは、災害に関しての役立つ最新情報を常に掲載し続けているが、例えばパーソンファインダーは災害発生から日にちが経つに連れ、必然的にニーズが下がってくる。個々のユーザーにとっては、安否確認ができれば再度訪れる必要がないからだ。ということは、前出の特設ページには、災害からの日数の経過に多じて、「緊急対策」から「復旧作業」へのシフトなど、適切な情報が変遷していくのかもしれない。ならば、「すべてのサービスを自社で用意する必要はなく、場合によっては他社のサービスをどんどん載せるべきだ」と徳生や三浦は考えていた。実際、Google のクライシスレスポンス特設ページには、Yahoo! JAPAN や助け合いジャパンといったボランティア活動へのリンクも掲載されていた。同様に、Yahoo! JAPAN にも Google クライシスレスポンスへのリンクを用意していた。
本連載は Google の Web ページに掲載される記事だが、2 回半にわたって Yahoo! JAPAN の取り組みを紹介した。同社の活動のすばらしさを教えてくれ、担当者を紹介してくれたのは、Google クライシスレスポンスチームの賀沢秀人で、他の社員も他社の取り組みについても学びたいと積極的だ。開発者リレーションの山崎富美も、Yahoo! JAPAN の取り組みを賞賛した上で「Google 社内でも被災地の物販の販売支援などの案が出たことはありました。しかし、それは我々の得意分野ではなく、Yahoo! JAPAN の得意分野です。災害直後のように特別な状況下では特に、それぞれが自分の得意な形で支援をするのが望ましいと思います」と語り、記事を書くことを応援してくれた。
それを聞きながら筆者(=林)が思い出していたのが、震災から数週間後の状況だ。当時、Twitter で数十万のフォロワーを持つ人の多くは、安否確認情報や被災地の重要情報などをリツイートで拡散することを重要な支援と考えており、筆者もその 1 人だった。当時、さまざまな個人や企業が、支援物資のマップや医療情報などの提供といった活動を始めており、取り組みが形になると、筆者や他の拡散力のある人に「こういったサービスを作りました。拡散してください」と頼んできた。しかし、中にはすでに他社が提供しているサービスと重複する内容のサービスも目立った。筆者の方で「これは〜〜のサービスと内容が近いのでくっついた方がよくないですか」と提案することもしばしばあった。その結果、「連絡を取り合ってみます」という返事が返ってくることもあったが、「あそことはやり方が違うので、うちはうちで進めます」という返事も多かった。
情報サービスはたくさん立ち上がれば立ち上がるほど、情報が分散してしまう。元となる情報の蓄積先(データベース)として同じものを共有していればその心配はないが、別のデータベースを持っていると、避難所の情報にしても、公衆電話の場所の情報にしても、支援物資や炊き出しの場所の情報にしても、分散してしまい役立たないものになってしまうことが多い。
別の取材で Safecast Japan というプロジェクトのリーダーと話をする機会があった。Safecast Japan は震災から 1 週間後に立ち上がったプロジェクトで、放射線測定機と GPS を活用して放射線量の地図を作っていた。このリーダーによれば、似たような取り組みをしている人達の意見にもできるだけ柔軟に耳を傾け取り込んできた、ということだった。
会社組織ではなく個人やグループで、情報活動をする人たちは、自分の信念を少し曲げてでも、多様な人を取り込んでいった方がよい活動ができるのかもしれない。
 Crisis
Response
Crisis
Response