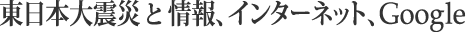この連載では、Google によるクライシスレスポンス(災害対応)を中心に取り上げてきた。しかし、災害対応を行っていた企業は Google 1 社ではない。規模の大小を問わず、さまざまな業界のさまざまな企業が、被災地の人々を助けようと奮闘していた。中でも、情報支援において Google と勝るとも劣らない存在感を示していたのが、ポータルサイトの Yahoo! JAPAN だ。
東日本大震災の発生直後から、Yahoo! JAPAN は地震情報のページを立ち上げて信頼性の高い情報の提供を始めた。そして、計画停電マップや募金、ボランティアへの支援などのサービスを次々に送り出した。こうした施策が可能だったのは、災害対応のための仕組みを普段から準備していたためである。
Yahoo! JAPAN の災害対応は、2004 年 10 月 23 日に起こった新潟県中越地震にまでさかのぼる。マグニチュード 6.8、最大震度 7 の中越地震は、死者 68 人、全壊家屋 3000 棟以上という甚大な被害をもたらした。
この頃にはすでにADSLや光ファイバー等のブロードバンド回線も普及し、テレビやラジオに並ぶメディアとしてネットが認知され、テレビ以上にネットを利用するユーザーも珍しくはなくなっていた。こうしたネットユーザーに災害情報を確実かつすばやく届けなければならない。中越地震を機に、Yahoo! JAPAN ではこのことを強く認識し、震度 3 以上の地震や津波については全ページに速報バナーを表示するようにした。
同時に認識されたのが、リスクマネジメントの重要性である。大災害が起こった場合、ポータルサイトとして情報発信を続ける必要がある。特に Yahoo! JAPAN には、新聞社や通信社からのニュースを掲載する「Yahoo!ニュース」とは別に、「Yahoo!ニューストピックス」がある。これは、数あるニュースのなかからYahoo! JAPAN の編集者が取捨選択し、その記事に関連するマスメディアや個人のブログなども含めた各種情報のリンクを付けて表示するサービスで、1 ヶ月の訪問者数は 7000 万人にも上る。そこで、Yahoo! JAPAN では、東京だけでなく名古屋、大阪にも拠点を設け、災害時のオペレーションを現場の判断で行える体制を整えた。
同じ 2004 年の 12 月に起こったスマトラ島沖地震や、2010 年のハイチ地震、同年の宮崎県における口蹄疫の流行等々、世界的な災害が起こるたびに、災害対応のオペレーションは実行されてきた。大災害についてテレビなどのメディアが報じると、より詳しい情報を求めてネットにアクセスする人が急増する。この受け皿となる情報をまとめて、Yahoo! ニュース トピックスで提供したり、募金の呼びかけを行ってきた。
 Crisis
Response
Crisis
Response