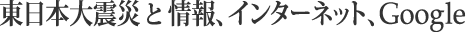2011 年 4 月はじめ、カメラマンの三井公一さんは、まだ交通網があまり復旧していない中、車で東北の被災地を目指していた。沿岸部の地域では地震や津波の影響で、通れなくなってしまった道路も多い。彼は、途中スマートフォンやタブレット、パソコンで、Google が提供する「自動車・通行実績情報マップ」を確認していた。
「通行実績」というのは、過去 24 時間の間に、その道を通った車があるか否かの情報だ。もし、周囲の道は車が通っているのに、ある道路だけ車が通った形跡がないとすると、その道はなんらかの理由で通れなくなっている可能性が高い。
IT に関するあるフォーラムで、Google の製品開発全般の責任者を務める徳生健太郎がこんな実例を披露していた。気仙沼近くの通行実績のない道路を Google マップで指し示した後、表示を航空写真に切り替えると、なんと道路の真ん中に巨大な船が横たわっていたのだ(地震後しばらく Google は、被災地の航空写真を頻繁に更新していた)。これでは車が通れるわけがない。
被災地を車で目指す人は、自動車・通行実績情報マップを使うことで、確実に車が通れそうなルートを見つけることができるのだ。
このように非常に便利な交通実績マップだが、これは Google の発明ではない。
交通関係に詳しいジャーナリストの神尾寿さんによれば、これは元々、防災推進機構が 2006 年に行った研究に、プローブ情報(自分がどこをどれくらいのスピードで走っているかという移動情報)を早くから(2003 年自動車メーカーとして世界で初めて)実用化していたホンダが協力して実現できたものだという。
ホンダの通信型カーナビ「インターナビ」を利用した会員制サービス、インターナビ・プレミアムクラブのメンバーは、道路交通情報通信システムセンターから提供される高速道路や幹線道路の渋滞情報を受け取るだけでなく、一般道の混み具合もわかる。同サービスでは、プローブ情報を PHS や 3G の通信経由で「利用者から」リアルタイムに提供してもらう。自分も情報を提供する代わりに、他のメンバーからの情報も受けることで、「どの道がどれくらいのスピードで流れているか」を可視化し、従来よりも詳細な道路の混み具合をわかるようにしていたのだ。
神尾さんによれば、この情報が、災害時に役立つことが実証されたのは 2007 年 7 月 16 日、中越沖地震が起きた時だという。この時の様子は同社のウェブサイトでも次のように紹介されている:
「地震発生後の走行データを抽出すれば、被災地における通行可能な場所をおおよそ特定できる。その情報を多くの人が共有できれば、通行できた道がより明確になり、救助や安否の確認に向かいやすくなる。
スタッフは翌日、フローティングカーシステムで集まった被災地における通行実績のあった道路情報を、防災推進機構に送った。」
 Crisis
Response
Crisis
Response