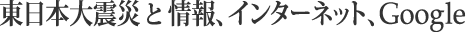東日本大震災のクライシスレスポンスでは、「コアチーム」と呼ばれた数人の社員が中心となって活動を行った。だが、このコアチームはもとから組織されていたわけではない。地震が起きた時点で災害対応を職務としていたのは、米国西海岸 Google 本社およびその他のいくつかのオフィスに分散しているクライシスレスポンスチームのメンバーだけであった。
日本のクライシスレスポンスは、クライシスレスポンスチームのプロダクトマネージャー(当時)だったプレム ラマスワミ(Prem Ramaswami)が、東京オフィスで知己のあったブラッド エリス(Brad Elis)に連絡を取り、「パーソンファインダー」を始動させるよう依頼したことから始まる。
ただし日本側でも、ウェブマスターの三浦健をはじめ、Google のクライシスレスポンスについて知識のあった何人かの社員は、活動を始める必要があるのではないかと話し始めてはいた。活動に積極的に関わりたいと思う有志の社員によって、チームは自然と形成されていった。
震災後、しばらくの間、通常業務を止めてクライシスレスポンスの活動に当たる社員もいたが、Google 社内ではそれを当然のこととして受け入れ、とがめる様子もない。
そうした体制を不思議に思う人もいるかもしれないが、Google 社員にとってはそれほど不思議でもなかった。なぜなら Google では、どんな業務をどんなやり方でいつ遂行するかは社員任せで基本的に自由となっているからだ。
今回、Google が極めて早く災害対応に当たれた理由は、会社として普段から災害対応の準備をしていたことによる。だが、それ以上に大きかったのは、平常時から根付いている仕事のやり方によるのではないか。他の企業で働いた経験を持つ Google 社員らに尋ねたところ、同じ意見が返ってきた。
そこで、まずは平常時の Google において、どのように仕事が進められているのかを簡単に紹介したい。
Google では、所属するチームにもよるが、仕事の進め方については(仕事を行う場所も含めて)本人の裁量の余地が大きい。
会社には仕事のスペース以外に、ビリアード台や卓球台、ゲーム機などの遊び道具もそこかしこに置かれており、これらで遊んでいる社員の姿も珍しくない。就業時間中に気分転換が必要とあれば、遊ぶことも自由だ。
社員にやりたいようにさせておけば、きちんと仕事をこなしてくれる。Google という会社は、社員を管理するのではなく、信頼して任せる。
また、就業時間のうちの20%(つまり月曜日から金曜日までの 5 日間のうち丸 1 日)は、自分の職務に関係のない好きなことを自由にやってよいという「20%ルール」が設けられている。Google ニュースや AdSense といった有名サービスのいくつかも、この「20% ルール」から誕生している。「20%」のプロジェクトにはエンジニアが 1 人で進めているものもあるが、大掛かりなチームで取り組んでいるものもある。社員は、プロジェクトの遂行上、必要な能力を持つ人材を社内(場合によっては社外ということもある)から探し出して自由にチームを作ることができる。
これは 10 年以上 Google を取材し続けてきた筆者(林 信行)の個人的印象だが、Google は膨大な手間とコストをかけてトップクラスの才能を集め、その能力を最大限に活かせるよう彼らを信頼し、主体性を尊重することで、モチベーションと会社への忠誠心を維持する企業文化を育んできたのではないかと思う。
これまでに取材をしてきた他の企業の中には、世界トップクラスの人材を雇い入れながら、その人がやりたくもなければ得意でもない仕事を与えて、才能とやる気を無駄にしてしまっている例が少なくない。それとは逆に、有能な人材にやりたいようにやらせた上で、成果を事業化していくのが Google のやり方なのだろう。
 Crisis
Response
Crisis
Response