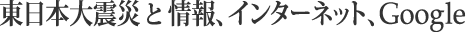3 月末時点において Google の災害対応(クライシスレスポンス)では 30 以上のサービスが立ち上がっていた。4 月 1 日までには、並行して進めていた他のプロジェクトも一通り形になり、新採用の社員達の出社も始まった。目まぐるしいペースで邁進していたクライシス レスポンスの活動に、自然と一区切りがついた。
もっとも、これは東日本大震災の状況が一段落したという意味ではない。
被災地では、まだ仮設住宅は作られておらず、相変わらず避難所暮らしを続ける人達が大勢いる。大都市の仙台市においても、ようやく電気、水道に続いてガスが復旧し始めたばかりという状態だった。
今後、被災地の人々に少しずつ平常を取り戻し、経済的にも復興をしてもらうために、Google がこの先できることは、まだまだたくさんある。クライシスレスポンスのコアチームの間では、それが何であるかは、東京にいてもわからないという共通の認識が広がっていた。
現場で Google を含めた情報系サービスはどの程度使われているか、どのような情報のニーズがあるのか。こうした調査を行うため「Go North (北へ行こう)」のかけ声の下、チームで被災地に足を踏み入れ、クライシスレスポンスの活動を第 2 フェーズに移すことになった。
これを受けて、製品開発全般の責任者で、米国開発チームとの橋渡しを務めてきた徳生健太郎は、クライシスレスポンス第 1 フェーズが終了したことを社内イベントで社員達に告げた。社員の中には通常業務を離れ、寝食を忘れてクライシスレスポンスに務めていた者もいたが、第 1 フェーズが終了した今、「Back to business」つまり、通常業務に戻ることによって有事の際にも役立つ基礎技術や製品開発に努めることも、これからの日本にとって大事なことだと説明した。ただし、一部の社員はこれからもクライシスレスポンスの活動を続けるため、彼らに仕事で協力を求めても対応が遅くなる可能性があることは付け加えた。イベントの様子は太平洋の反対側にも伝えられ、米国本社のクライシスレスポンスチームに大きな安堵をもたらした。
さて、例年であれば、4 月 1 日になるとあちこちのウェブサイトでジョーク企画が競い合われるものだ。2011 年 4 月はまだ日本中が重苦しい雰囲気で包まれていたが、Google ではみんなが幸せになれるちょっとした「嘘」をつくことにした。Google は、小中学生を対象にホリデーロゴ(記念日などに Google のトップページに表示されるロゴ)を募集する 「Doodle 4 Google」コンテストを開催しており、2009 年のテーマは「私の好きな日本」だった。本来は優勝作品だけが掲載されることになっていたが(優勝作品は 2010 年に掲載されている)、4 月 1 日限定で、日本全国の各地区から選ばれた代表作品全 30 作を Google のトップページで紹介したのだ。
 Crisis
Response
Crisis
Response