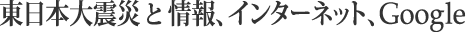まだ大きな余震もつづいていた震災直後の最初の週末、多くの人々は家にこもってテレビやラジオで状況を見守っていた。
インターネットにアクセスできた人々は、被災地の被害の状況や水・食料などの支援、そして原子力発電所や電力の状況について、より早く情報が伝わってくる Twitter などのソーシャルメディアで情報を収集していた。地震の直後から、Twitter は被災地にいる人々や各分野の専門家の意見を得ることができる、有用な情報獲得ツールとなっていた。
この Twitter 上でのやりとりを通して、必要な人に必要な情報を届ける「情報支援」という形の支援があることに多くの人々が気づき始めた。最初の週末だけでも、各種サバイバル情報や Google のマイマップにまとめ直した公共情報といったコンテンツから、個人やプログラマーグループが独自に開発した安否確認や避難所情報などの情報交換サイトまで、次々と情報支援の取り組みが立ち上がり始めた。
3 月 11 日、地震直後の初動で Google が公開したのは、パーソンファインダーや衛星写真、混乱していた鉄道の運行状況がわかる「鉄道遅延情報」など、Google がすでに持っていた技術や情報を元につくられたサービスが多かった。
しかし、それが一段落すると、他社との協力の下で情報提供するサービスに自然と軸足が移っていった。非常時に何か人に役立ちそうな情報があれば、その情報を持つのが他の企業であれ、機関であれ、組織であれ、かまわずに声をかけ、連携を呼びかけていった。
パーソンファインダーも初期の段階では、Google が独自に広報をして登録を呼びかけたが、その後はまず NHK がテレビで提供していた安否確認の情報を統合。新聞社や携帯電話事業者、警察庁の情報も加わった。さらに、避難所にいる人々の名簿を携帯電話のカメラで撮影し、インターネット上のボランティアが書き起こすという形でデータ化した「避難所名簿共有サービス」が加わり、最終的には 67 万件以上の登録がある巨大なデータベースが放送局や通信事業者の間で共有された。
避難所情報についても同様のことがいえる。当初は Google 社員が自ら避難所に関する情報を集めていたが、その後毎日新聞社からの情報が加わり、17 日(木)には個人や報道機関等が情報を入力できる専用フォームが追加されている。
 Crisis
Response
Crisis
Response